1.トルイチ将棋とは?
「取る一手将棋」を略して「トルイチ」と呼んでします。ルールは単純明快で、本将棋のルール+「取れる駒がある時は必ず取らねばならない」というものです。例えば、下図は初手から▲76歩△84歩と進んだ局面です。
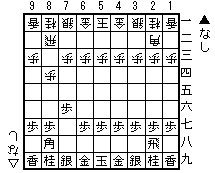
普通は先手はここから▲26歩とか▲56歩とか▲66歩と指して駒組みを続けていくのですが。トルイチだとそういうわけにはいきません。
トルイチの場合ここでの先手の絶対手は▲33角成なんです!
何故かというと、この局面で33の地点の歩を取ることができるからなんです。
トルイチ将棋は初手から落とし穴の連続です。慣れるまでは「あ、しもた……」の連続かもしれません。
だけど、角損したからと言ってすぐに悪くなるわけではないのがトルイチの深さでもあります。
ルール
1、特殊状況(駒が取れる等)以外の場合は全て本将棋のルールに従います。なので、相手の王様を詰ませば勝ちというのも変わりません
2、駒を取ることができる場合は必ず取る手を優先しないといけません。2通り、3通りと駒を取れる場合はどれから取っても構いません
3、トルイチの例外は王手です。王手に対しては別に取る必要はありません。逃げても構いません。また、王手でなくともその駒を取れば直後に王を取られてしまうというケースもとる必要はありません。
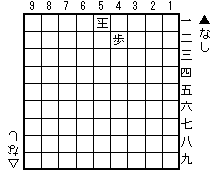
(後手の手番)↑この歩は王手ではないので取らなければならない。
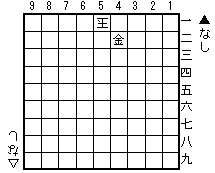
(後手の手番)↑この金は王手なので選択が可能。
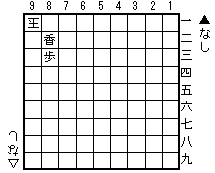
(後手の手番)↑普通の駒なら△88玉と取らなければならないが、直後に歩で取られてしまう。本将棋でも禁じ手の類であり、後手は△88玉と取る必要はない。
2.トルイチ将棋の魅力
トルイチ将棋の魅力は何と言っても終盤です。本将棋の終盤よりパズル的なスリルを味わうことができます。
また、「何でこんな局面から詰むの?」というような遠距離からの打撃が可能なことも面白い理由です。
気がついたら切られていた。そんなスピード感がウリです。
例えば筆者が試みで作ってみた局面を見て下さい。
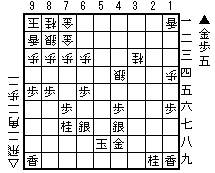
図1は△44同銀まで。
局面は先手が44の地点の歩を角で取り、それを銀でとられたという設定です。
手番は先手が握っているものの、本将棋なら必敗と言っても過言ではありません。なんせ、相手は穴熊の堅陣。こちらはスカスカの中住まい。そして駒の損得は先手の「飛車角損」です。
筆者が本将棋で先手番を持っていたとするならば少なくとも10手前には投了している局面です。
ところがこれがトルイチ将棋だとしたら話は変わってきます。
なんとこの局面は先手が単純明快に一手勝ちなのです!
図1以下の指手
▲9四歩 △同 歩 ▲同 香 △同 香 ▲8四歩 △同 歩
▲8五桂 △同 歩 ▲6四歩 △同 歩 ▲6三歩 △同 金
▲5四歩 △同 金 ▲6二歩 △同 金 ▲8三歩 △同 銀
▲8四歩 △同 銀 ▲1五歩 △同 歩 ▲同 香 △同 香
▲1九歩 △同香成 ▲8三歩(まで図2)
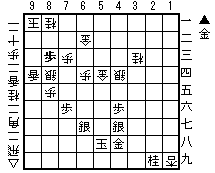
図の局面では後手は19の成香で29の桂馬をとらなければなりません。次の絶対手は△29成桂です。
そして先手に手番が廻り、▲82金迄で後手玉の詰みとなります。
連続駒捨てで穴熊がいとも簡単に崩壊してしまいました。最後に出てきた端に成香を呼び込む手はトルイチにおいて必須手筋ですので覚えておいて損はないでしょう。
参考例で見たように、トルイチ将棋の形勢判断に駒の損得はそこまで関係がありません。
また、王様の固さも本将棋のそれとは違った感覚が求められているようです。
図1が先手番だとするとある程度上達すれば上の勝ち手順は比較的短時間で見えるようになります。
ですが、図1で手番が後手だとすると明快な勝ちをすぐに発見することは至難の業でしょう。
(一応、△88飛から金を入手して、玉を下段に落とし、最終的に33の桂を先手に取らせる形を作ることで勝ちではありそうだ→だが、△88飛には▲69玉と逃げる妙手がある。実は相当に難解なのだ)